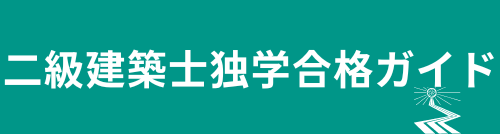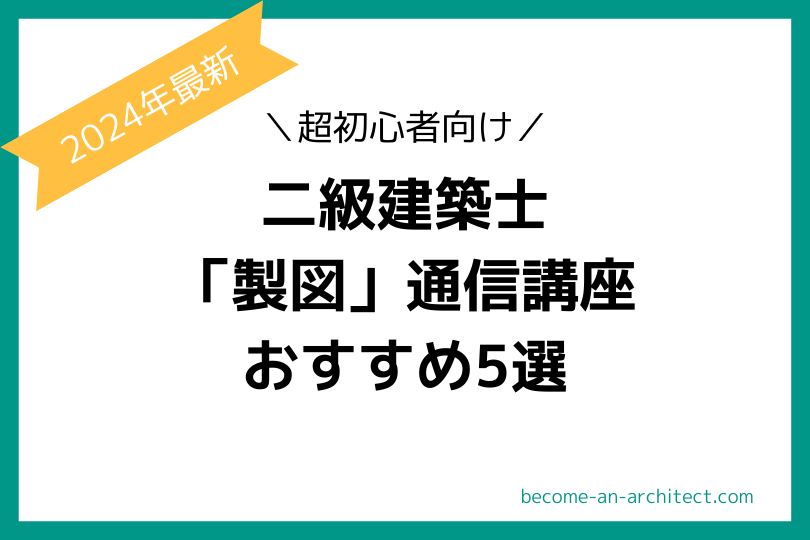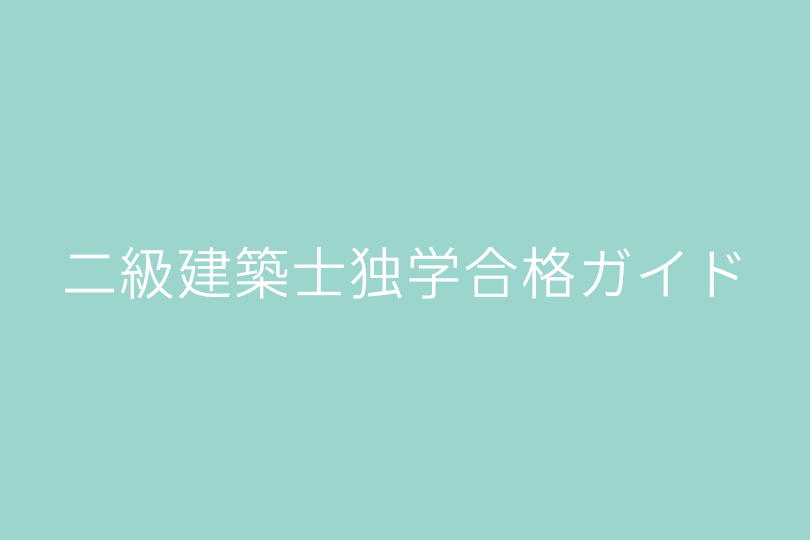こんにちは!くりです。
ぼくは独学で二級建築士の製図に合格しました。
大学ではほとんど製図をしていないので、ほぼ知識ゼロからの出発です。
勉強を始めた時は、とにかく不安と心配でいっぱいでしたが、無事合格することができました。
ちなみに1年目は不合格、2年目で合格しています。
失敗したときの原因を含めつつ、
二級建築士の製図独学勉強法
を紹介します。
※ぼくはフリーランスで時間の余裕がある感じです。あくまでも参考程度でお願いします。
この記事は、「【独学】二級建築士の勉強法【製図編】」を書いていきます。
目次
二級建築士「製図」の基本情報
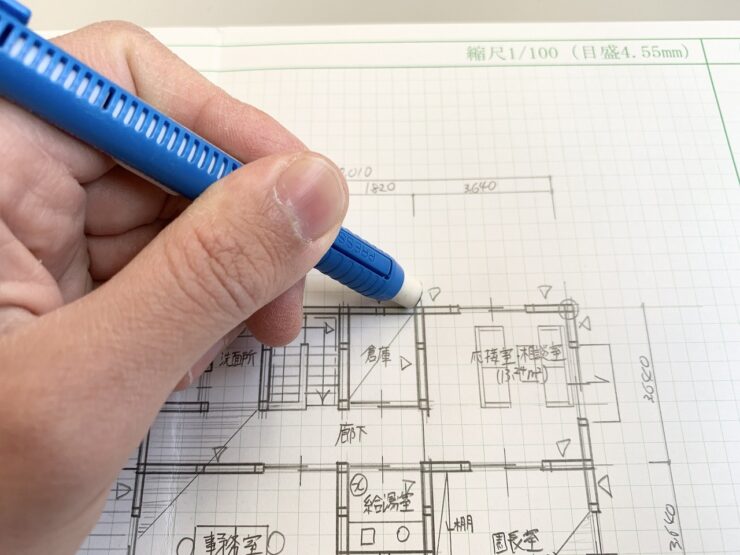
二級建築士の製図は、学科を突破した人のみ受けることができる試験です。
毎年9月上旬に行われます。
学科試験が終わってからは、2ヶ月と数日しかありません。
その短い期間で、「合格基準を超える製図」ができるようになる必要があります。
※もちろん学科と並行して製図の勉強をすれば、その分有利です。
試験時間
試験時間は5時間です。
5時間座ったまま頭をフル回転し、ひたすら線を引いていきます。
11時スタートなので、昼ごはんも食べられません。(なので試験前に食べる)
こんな特殊な試験は、建築士くらいでしょう。
※出典:試験について (3)試験日・時間割|公益財団法人 建築技術教育普及センター
採点基準
製図の採点は、結果のみ知ることができます。
以下の4種類に分けられます。↓
| ランクⅠ | 「知識及び技能」を有するもの |
| ランクⅡ | 「知識及び技能」が不足しているもの |
| ランクⅢ | 「知識及び技能」が著しく不足しているもの |
| ランクⅣ | 設計条件・要求図書に対する重大な不適合に該当するもの |
ランクⅠのみが合格、それ以外は不合格です。
※出典:令和4年二級建築士試験 「設計製図の試験」の合否判定基準等について|公益財団法人 建築技術教育普及センター
ちなみにぼくは、
- 一年目:ランクⅢで不合格
- 二年目:ランクⅠで合格
になりました。
表を見るとわかりますが、うまく製図をするというより、
二級建築士として最低限の知識&技能を身に着けているか
を見られていると思います。
合格率
過去5年の「製図の合格率」は以下のとおりです。
| 2023年 | 49.9% |
| 2022年 | 52.5% |
| 2021年 | 48.6% |
| 2020年 | 53.1% |
| 2019年 | 46.3% |
※出典:過去5年間の二級建築士試験結果データ|公益財団法人 建築技術教育普及センター
例年約50%、2人に一人が合格しています。
こう見ると「へぇー、意外と行けそうじゃん」と思いますが、学科を突破してる真面目な方のみ受けている試験です。
その中で2人に一人は振り落とされる、そこそこ厳しい戦いになります。
ちなみにぼくが初めて受けた年には、RC造の ”地面の傾斜” というサプライズが出て、対応しきれずに不合格でした。
「地面の傾斜って、なんだよ、、、年一でしか受けられないんだからベーシックな問題を出してくれよ…」
と不満に思っていましたが、上位約50%は合格しているので、ただの実力不足でした。
もちろん、その逆もしかりです。
二級建築士「製図」の独学勉強方法
ここからは実際にぼくが行った、二級建築士「製図」の勉強方法を解説していきます。
この勉強方法で、ぼくは合格できました。
1.「設計製図テキスト」を7周する
製図の勉強に入る前に、ネットで情報収集をしました。
そこで多くの方におすすめされていたのは、「総合資格学院 設計製図テキスト」です。
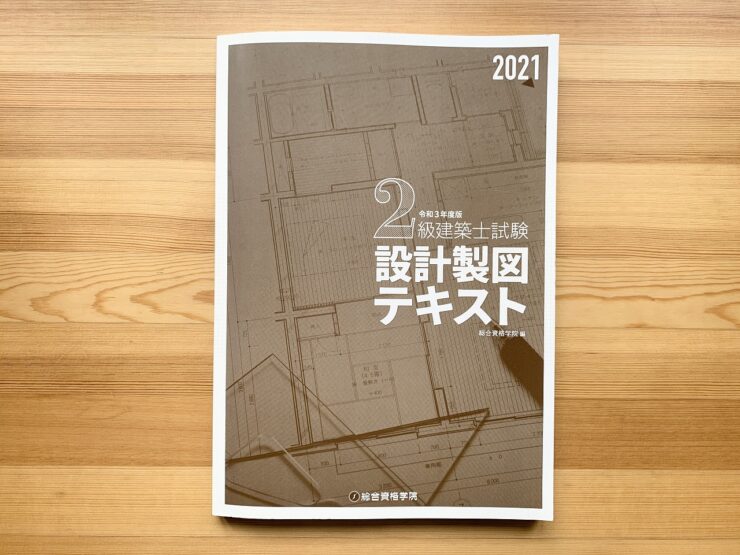
この参考書には、製図の書き方が書いてあります。
- 木造
- RC造
- 鉄骨造
の3種類が載っていて、自身が受ける年の問題に合わせて使います。
ちなみに、本試験は「木造→木造→RC造」のサイクルで繰り返されています。
ぼくは一年目はRC造、二年目は木造でした。
2種類ともこの参考書に載っていたので、買い直さなくてすみました。値段が少々高いですが、3種類も載っていてお得です。
あと受けるのに必要な情報(製図する流れ、エスキスの方法など)が書いてあります。
個人的に、とてもクオリティの高いテキストだと思います。
- 持ち物など基本から解説
- 「線1本の書き方」をカラーで解説
- 見本をまねるだけで習得できる
まさに資格学校のテキスト。少しお高めですが、内容からするとむしろ安いなと。
独学ならこの一冊が必要です。↓
この参考書に載っている書き方で、同じものを7周してください。
※ぼくは時間があったので、11周しました。
最初は、かなり時間が掛かります。
ぼくも1枚書き上げるのに、3日位かかり、
「これ、本当に独学でいけるのか…?」
と絶望しました。
しかし、試験が終わったので言えます。
書けば書くほど、書くのが早くなります。
なのではじめが一番時間がかかります。諦めずに、コツコツと書き続けてください。
※使う製図道具は、「【保存版】二級建築士で使う「製図道具」まとめ」でまとめています。
ポイント:深く考えない
ここで一つポイントがあります。
とにかく深く考えない
ことです。
ぼくがはじめたとき、
「この線、何を表しているんだ?」
「なんで太線なんだろう?」
と頭がはてなだらけでした。
しかし、考えるだけムダです。初学者が考えても、理解できることはありません。
そして考えても、ただ時間が過ぎるだけです。
例えば、スイッチを押すと電気はつきますが、「なぜ電気がつくのだろう?」と考えても答えはでないですね。
これと同じです。
ぼくは考えすぎて、時間をムダにしてしまいました。
今だからわかりますが、練習量が増えればふえるほど、勝手に理解度も増していきます。
その時に理解できれば十分。
なので、何度なんども書いて、手に覚えさせて、本番で再現するだけでオッケーです。
製図用紙はこちらを使います。↓
※2024年度はおそらく鉄筋コンクリート造になります。
独学者が製図用紙を手に入れる方法は、おそらくこれ一つです。
本番同様の紙が使われていて、当日も慣れた練習と同じように書くことができました。
ちなみにぼくははじめケチろうとして、ネットから印刷したものを使っていました。
しかしなぜかマス目と定規が合わずに、
「製図の定規って特殊なのか?それともいつもと違う測り方なの?」
と悩んでしまいました。
3日ほど絶望したのち、それでも分からず、ついに製図用紙を買いました。
まあ、印刷したときに少し縮小されてしまっただけなんですけど…。
こんなムダな時間は必要ないので笑、普通に製図用紙を買いましょう。
↑ こんなムダな悩みは、製図独学でたくさんあります。なのでそれに惑わされず、「まあいつか分かるだろw」みたいなモチベーションで書き続けてください。
2.「設計製図課題集」をとにかく書き写す
製図の書き方がわかり始めたときに、課題集に移ります。
次は、「総合資格学院 設計製図課題集」です。
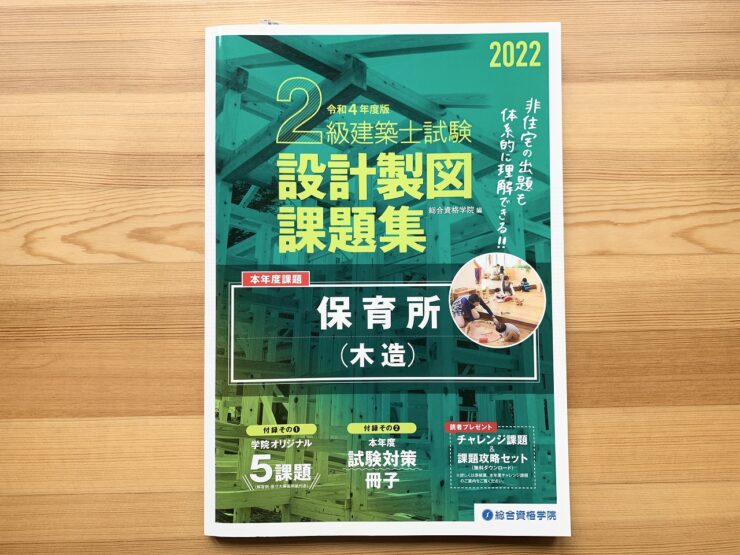
毎年6月頃、二級建築士製図の課題が発表されます。
ぼくの時は、「保育所」でした。
その後1ヶ月ほどで「保育所」の課題集が各社から発売されます。
ぼくは総合資格学院の課題集を選びました。こちらも独学者の定番です。
※課題発表後に、そのテーマに沿うものが発売されます。
この課題集を、とにかく書き写します。
課題は5つ収録されています。
※この本に「折りたたまれたA2の紙」が付属しています。課題5枚と図面5枚です。
ぼくは7周ずつ書き写すことを目標としました。
それでも時間が足りず、結果的に
- 課題①:8周
- 課題②:8周
- 課題③:8周
- 課題④: 3周
- 課題⑤:8周
という枚数を書き写すことができました。(本番同様に見本なしで書いたものも含む)
順番的には、
- 課題①を7周
- 課題②を7周
- 課題③を7周
- 課題⑤を7周
- 課題④を2周
- 模試(1枚)
- 課題①を何も見ずに1周
- 課題②を何も見ずに1周
- 課題③を何も見ずに1周
- 課題④を何も見ずに1周
- 課題⑤を何も見ずに1周
- ☆本番☆
という流れです。
関連記事:二級建築士の製図、何枚かけば合格できる?【ぼくは47枚書いた】
※働きながらで一年目の方がここまで書くのは、時間的に厳しいと思います。
なので、
一年目に全力でやって受かったら儲けもの、二年目で必ず合格する
という感じでやったほうがいいと思います。
一年目で受かる人は本当にすごいです。ぼくには無理でした。
なので、自分のペースを守って、合格を目指しました。
※資格学校や通信講座を利用する方は、全力で一年目で合格を目指しましょう。
二級建築士の製図は、3回チャンス(学科免除)があります。
裏を返せば、
「一年目で受からなくても、次できればいいんだよ」
と建築センターが言ってるようなもの。
話が脱線しそうなので、「二級建築士の製図試験、落ちてました…(追記:2年目で合格しました!)」で少し解説しています。
ポイント1:少しずつ見本なしで書く
課題集の書き写しが進み、すらすらと製図ができてくると思います。
そこで、少しずつ見本なしで書いていきましょう。
- 一切見本を見ないのではなく、
- 得意な図だけ見ないようにすると、
- ストレスなくできます。
ぼくは立面図が比較的に書けたので、はじめはそこだけ見本を見ないようにしました。
本番(模試)までに何も見ずに書ければいいので、焦る必要はありません。
焦って見本なしで書いて、「全然できないじゃん…」みたいに心が折れてしまうと元も子もないです。
なので、自分のペースを守りつつ、コツコツ進めることが大切です。
※音楽やオーディオブックを聞きながら、リラックスしつつ製図するのがおすすめ。↓
ポイント2:エスキスを始める
製図が安定してきたら、エスキスも始めましょう。
はじめは図面を見ながら、エスキスを書いて練習します。
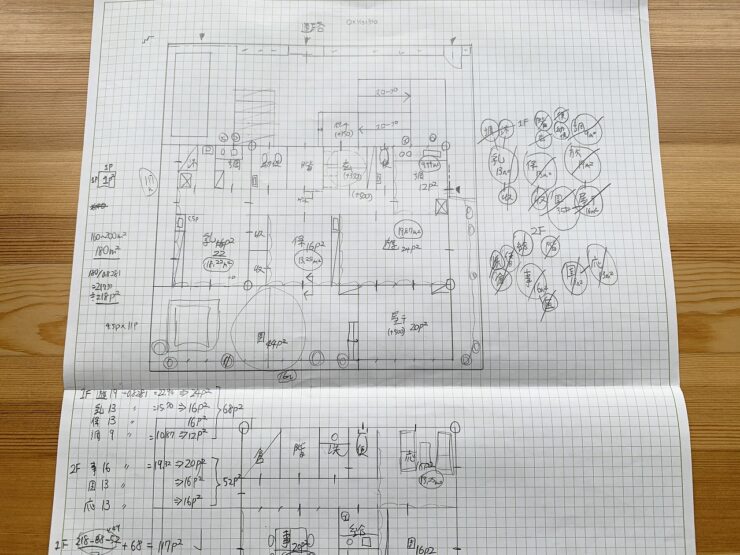
できるようになったら、課題文だけを見て、エスキスを書いていきます。
エスキス用紙はこちら。↓
※2024年度はおそらく鉄筋コンクリート造になります。
ぼくは本番までに、18枚ほどエスキスを書きました。
けれどこれでも苦手だったので、もっと練習すればよかったなと思っています。
エスキスも書けば書くほど、得意になります。
3.模試を受ける
模試は必ず受けましょう。
現在は日建学院が、本番1週間前に模試を行ってくれます。
模試を受けると、目標が模試に設定できます。
なので、本番では「今までの練習+模試の反省」で勝負できます。
模試なしで本番を迎えてしまうと、自分の苦手が分からずに特攻することになります。
それを避けるために、できるだけ受けることをおすすめします。
ちなみにぼくは、
- 一年目に模試なしで本番で失敗し、
- 二年目は模試を受けて、成功しました。
模試の効果は絶大です。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。↓
・二級建築士の製図「模試」を受けるメリット3つ【必ず受けよう】
その他疑問
この勉強法で、想定される疑問に答えてみます。(というか、当時ぼくが抱いていた疑問)
課題集は何冊もやったほうがいいの?
A.何冊もやる必要はありません。
ぼくは1冊を何度もなんども繰り返す方法でいけました。
ただ、これは本当に人によります。
ネットを見ても、
3冊の課題集を買い、すべてを2~3周する方法
で合格している人が結構います。
ぼくもその方法をマネするか考えました。
ですが、その方法で上手くいったことがないので辞めました。
すべてをつまみ食いして、理解出来るようになることは、頭の優れた人しかできない気がします。
自分に合った方法を選びましょう。
本当に製図独学でも受かるの?
A.受かります。
ぼくが証明です。
ただ、人に独学を勧めるかというと、、、ちょっと微妙だなと。
二級建築士の製図は、簡単に◯✕で判断できないので、一人でやるにはかなり無理がありました。
なので資格学校や通信講座を利用して、無理なく合格を目指すのが良いと思います。
指導者がいると迷う時間を省くことができて、製図も少ない枚数で合格できます。
ただ当時のぼくと同じように、とんでもなく金銭的余裕が無い方は独学でがんばりましょう!
しかし、「まあちょっとくらい未来のために投資できるよ」という方は、ぜひ資格学校や通信講座を利用することをおすすめします。
そして全力で合格を狙ってください。
落ちたら来年、というのは結構キツイです。(経験談)
こちらにおすすめの通信講座をまとめました。興味のある方はご覧ください。↓
・【合格者が選ぶ】二級建築士「製図だけ」の通信講座おすすめ5選
まとめ
この記事は、「【独学】二級建築士の勉強方法【製図編】」を書きました。
製図はとにかく書き写すことがポイントです。
そして細かいことを深く考えないのも大切。
書けば書くほど、早く書けて、理解度も増します。
とはいえ、焦りは禁物。
自分のペースを守りつつ、焦らずコツコツ進めていきましょう。
※2024年度はおそらく鉄筋コンクリート造になります。