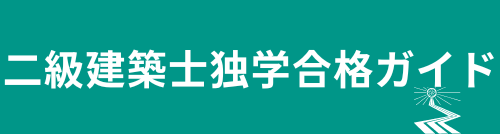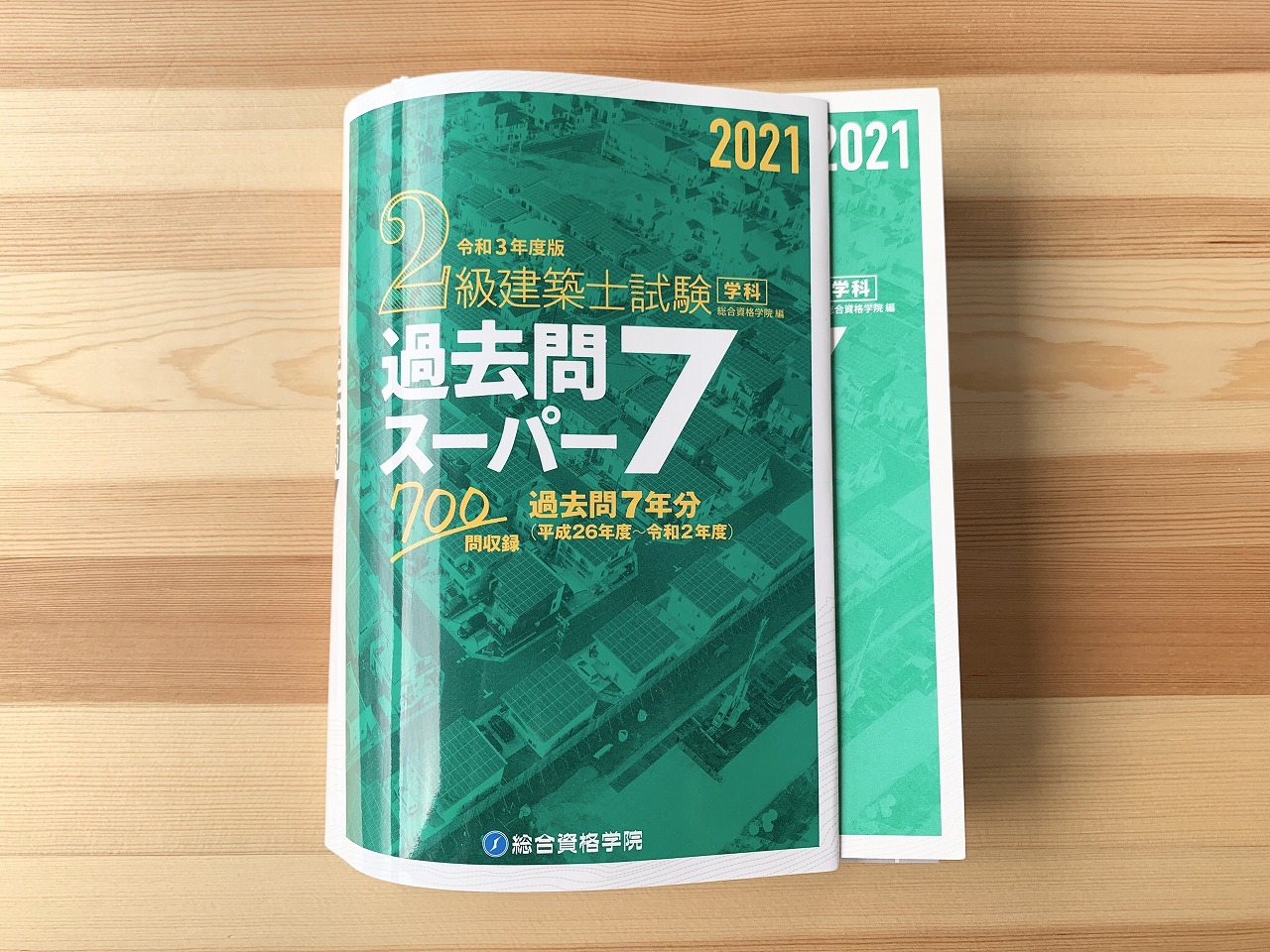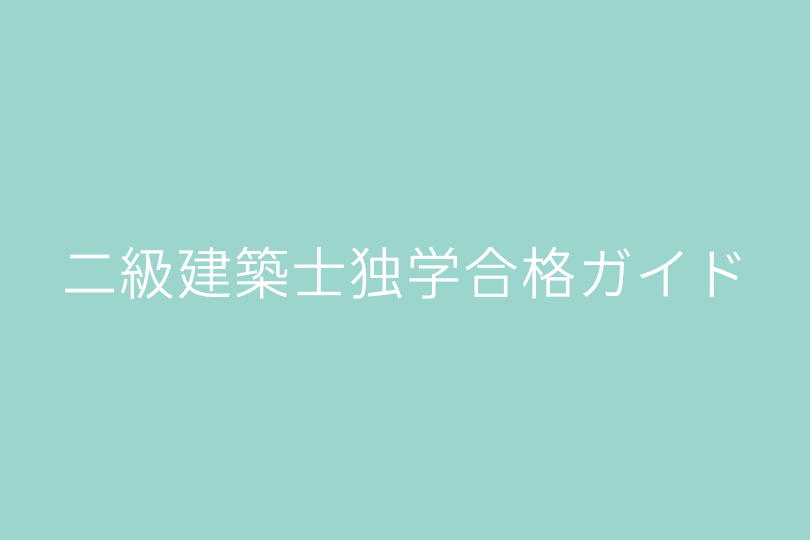こんにちは!くりです。
ぼくは独学で学科を突破しました。
法規は一番得点をとることができ、本番では22点(25点中)でした。
しかし得意というわけではなく、勉強を始めたのも6月からです。(ぼくは時間のあるフリーランス)
それでも高得点が取れたので、ここのその時の勉強方法をまとめてみます。
なお、計画・構造・施工は別でまとめています。↓
この記事は、「【独学】二級建築士の勉強方法【法規編】」を書いていきます。
目次
二級建築士の法規とは?基本知識まとめ
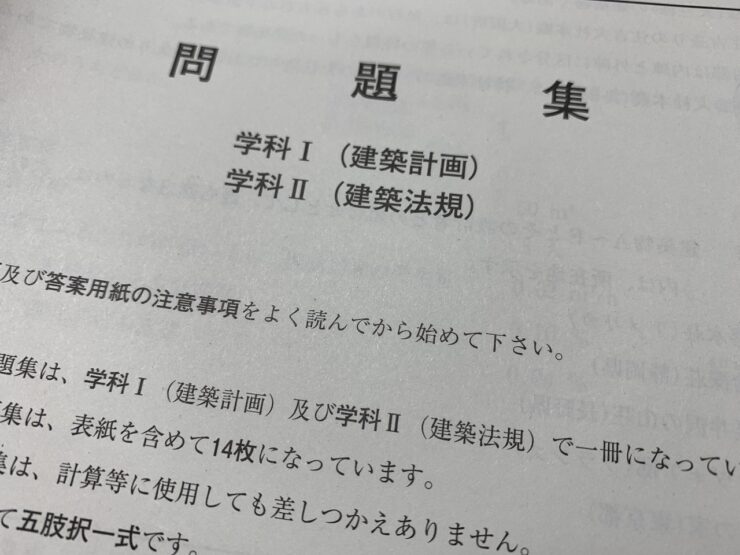
まずは簡単に「法規」のおさらいをします。
二級建築士の学科は、
- 計画
- 法規
- 構造
- 施工
の4つに分かれています。
そして試験時間は、
- 計画+法規:計3時間
- 構造+施工:計3時間
になります。
つまり3時間以内で「計画と法規」をこなします。
※出典:出題科目、出題数等|公益財団法人 建築技術教育普及センター
法規で取るべき得点
学科のそれぞれの得点は、以下のとおり。↓
- 計画:25点
- 法規:25点
- 構造:25点
- 施工:25点
全部で100点満点です。
学科を突破するには、以下の得点が必要です。
- 合計60点以上
- 各科目13点以上
4科目の合計が60点以上かつ、それぞれが13点以上を取らなければいけません。
※出典:令和4年「学科の試験」の合格基準点等について.pdf|公益財団法人 建築技術教育普及センター
ここまで読んだら、
「じゃあ60÷4=15で、法規は15点取ればいいんだね~」
と思うかもしれません。
ぼくも初めはそう思っていました。
しかし!法規は特殊な科目なので事情は変わります。
法規は法令集を持ち込むことができます。
全力でやれば満点を取ることも可能です。
なので、法規は満点を取る気持ちで望みましょう。
ぼくは施工が苦手だったので、「法規でカバーするようにしよう」と思っていました。
そして施工15点、法規22点と思った通りになりました。
ただ、一つ注意なのが、
法令集持ち込みOKなために、油断する人が結構いる
ということ。
法規を軽視し、法規のみ基準点を取れずに落ちる、という方を結構見ました。
なので油断せずに全力で取り組みましょう。
法規を学ぶ前に知りたい注意点
次は、ぼくが法規を学ぶ前に知りたかった、注意点をまとめてみます。
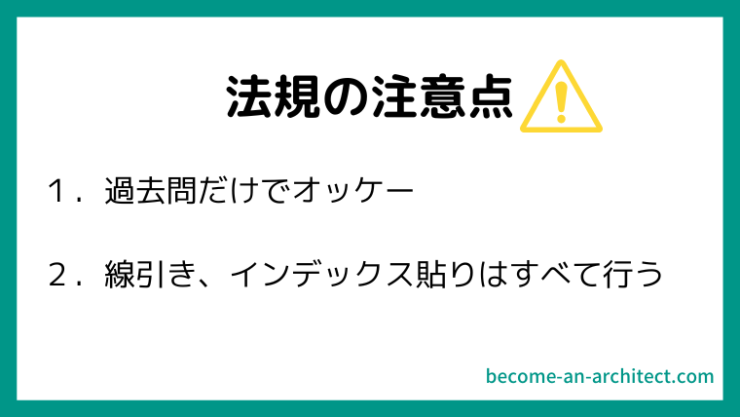
1.過去問だけでオッケー
まず法規は、過去問だけで高得点を取ることができます。
はじめて法規の問題を見ると、
「なんだこれ…?漢字多すぎだし、イミフすぎる」
と絶望すると思います。
(ぼくも4月にはじめて法規をみて絶望し、法規は後回しにすることにしました。笑)
絶望した時、こんなことは思わないでください。↓
「なんか裏技とかありそう。他の書籍を買ってみよ」
これはNGです。
時間のムダ。
はっきり言って、法規は過去問を周回すれば超ラクに解ける教科です。
何度もなんども過去問を解いていると、5つの選択肢のうち、法令集を見なくても2択に絞れるようになります。
法規に、
- 「裏ワザ」とか、
- 「合格者しか知らないマル秘テクニック」とかないので、
とにかく過去問を周回してください。
2.線引き、インデックス貼りはすべて行う
ぼくも法規がナゾだった頃、ネットで色々調べてみました。
そこで、
「線引きやインデックス貼りは、よく使うところだけにしよう」
と書いてあるのをよく見ました。
単純なぼくは、
「ほーん、そうなんだ、じゃあそうしよう」
と信じていましたが、これは微妙でした。
いちいち貼るか貼らないか悩むのが、超めんどくさかったです。
「ここは貼ったほうがいいのかな?ここ貼ったら、あそこも貼ったほうがいいよな」
と悩むのは、ストレスが半端なかった。
そこで途中で線引き・インデックス貼りをすべて行ったところ、ストレスがだいぶ減りました。
ネットでよく見た、
「インデックスは邪魔!」
というのも、人によるなと思いました。(むしろ無いとできない)
頭がいい人なら、よく使うところだけでいいかもしれません。
しかしぼくのような凡人なら、線引き・インデックス貼りをすべて行うべきです。
いちいち、
- 線を引くか引かないか
- インデックスを貼るか貼らないか
で悩んでいたら消耗します。
そこで力を使うなら、過去問で一問でも多く解いたほうがお得ですね。
二級建築士の勉強方法【法規編】
ここからは、独学で合格点が取れる法規の勉強方法をまとめてみます。
以下のとおりです。↓
1.「二級建築士 はじめの一歩」を1周読む
まずは、「二級建築士 はじめの一歩」を1回読みます。
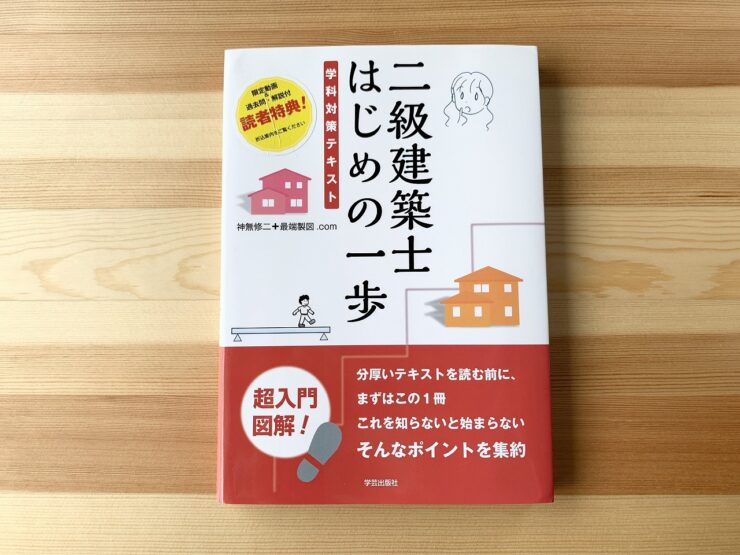
この本は、二級建築士の入門書です。独学者のみかた。
法規の部分を1回読んで、「法規とはどういうものか」を把握します。
サラッと流し読みしてください。
じっくり読んでも、どうせ忘れます。
あとは辞書的に使います。
2.法令集の線引きをする
次は、法令集の線引きを行います。
法令集はどれでもいいと思いますが、おすすめはTACの法令集。
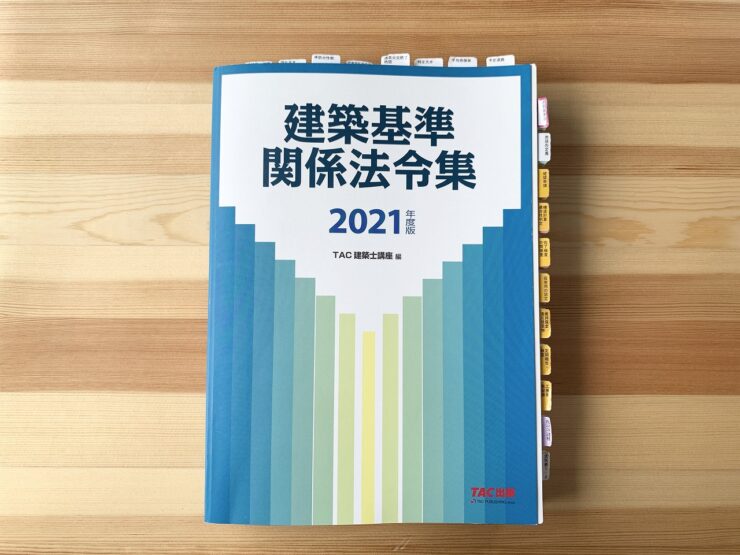
TACの法令集のいいところは、
- 線引きの見本がネットで見れる
- 分冊できる
- B5サイズで見やすい
ことです。
ほかの法令集って、線引きの見本を手に入れるのに手間がかかるんですよね。S学院の法令集では、はがきを送らないと手に入らないらしいです。(さらに勧誘の電話が来るらしい)
そんなのめんどくさすぎるので、TACにしましたがこれが大正解。
あとほかの法令集ってぶ厚すぎ…。
ぼくはやる気を削がれる気がします。
TACは比較的薄いので、心理的負担になりません。
2冊のセパレートタイプなので、ページをめくりやすいです。
独学者には、TACの法令集一択だと思います。
関連記事:二級建築士で使える法令集おすすめ5選
線引きを行う
TACの法令集と、線引き用のマーカーが手に入ったら、まずは線引きをしましょう。
参考:TAC 建築基準関係法令集 2024年度版(必要なマーカーも載っています)
見本を見ながら、どんどん線引きを行います。
線引きのポイントは、2つ。
ポイント1つ目は、「関係法令」からやることです。
1ページ目からやると、永遠に終わらない感じがします。そして挫折します。
なのでそれを防ぐため、途中の「関係法令」から線引きをするとストレス軽減できました。
ポイント2つ目は、「一日でやらないこと」です。
ネットで、「線引きは地獄」とよく書かれていましたが、全員1日で終わらそうとしてました。
それはつらすぎます。
ぼくは1週間かけて、線引きを終わらせました。
1日1~2時間、音楽をかけながら、何も考えずにマーカーを引いてました。
計画の問題を解くより、全然ラクです。
3.インデックスを貼る
次はインデックスを貼りましょう。
インデックスとは、ページを開きやすくする目次のシールです。
こちらも、TACのホームページに貼る箇所が見れます。
思ったより時間がかかるので注意です。
4.過去問を7周する
ここからが本番、過去問を7周しましょう。
ぼくは7年分を7周するつもりでした。しかしハプニングが起きて、5年分7周しかできませんでした。
それでも22点取れたので大丈夫でしたが、7年分やったほうがもっと本番で時間が余ると思います。
5~7年分を、7周すれば合格点は取れるでしょう。
ぼくが使っていた過去問は、総合資格学院のものです。↓
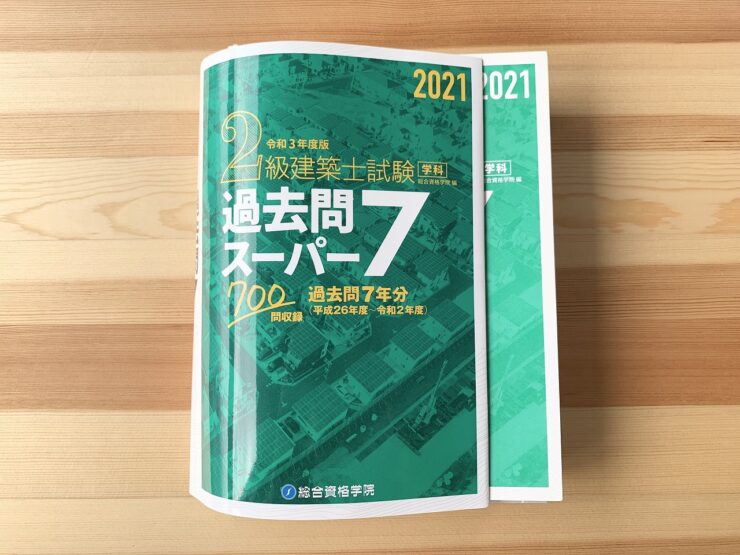
関連記事:二級建築士「学科」の過去問おすすめ4選
ぼくははじめ、答えの写真をとったスマホを上に置いて、答えを見ながら進めてました。
一番初めは、分からなすぎて答えを見ながらでしかできなかったからです。
最初は3問解くだけで、1時間とかかかります。
けれどそこで諦めず、がんばって進めてください。
どんどん、一問にかかる時間が短くなってきます。
法規は高得点を取れる科目。なにより暗記しなくてもいいので、点数が安定します。
こんなラッキー科目を軽視するのはもったいないです。
ちゃんと答えだけではなく、選択肢をすべて、法令集で確認してください。
その積み重ねが、どんどん点数を安定させていきます。
最後の方になると、問題文を読んだだけで、マーカーの色と形が頭に浮かんできました。
この状態になれば、合格点は余裕で取れます。
ポイント:答えをすぐ見る
ポイントが一つあって、それはわからない問題があればすぐに答えを見ることです。
法規は「ぎりできそう」と思わせる科目。
なので自分に失望したくなくて、分からない問題でも、自力で探そうとしてしまいます。
けれどこんなことを繰り返していると、ストレスが蓄積していきます。
それでついに、
「あーあ、法規めんどくさ、持ち込みできるし、あとはなんとかなるでしょ」
と思い本番で11点と、ぎりぎり足切りされる点数をとることになるでしょう。
法規で分からないことがあったら、すぐに答えを見てください。
そしてめんどくさがらず、ちゃんと答えまでの手順通り進めてください。
努力を積み重ねていけば、本番で焦ることはなくなります。
あとは一周ごとに、正の字で数えてました。
7つ貯れば、完了です。
まとめ
この記事は、「【独学】二級建築士の勉強方法【法規編】」を書きました。
最後にまとめます。↓
法規は、いかにストレスなく進められるかが重要だと思います。
ストレスを排除して、高得点を狙いましょう。
以上です。応援しています!
▼この3冊で、法規22点(25点中)取れました。
計画・構造・施工の勉強法はこちら。↓