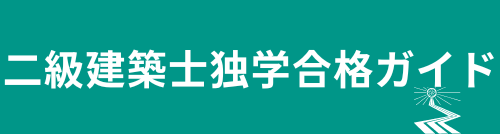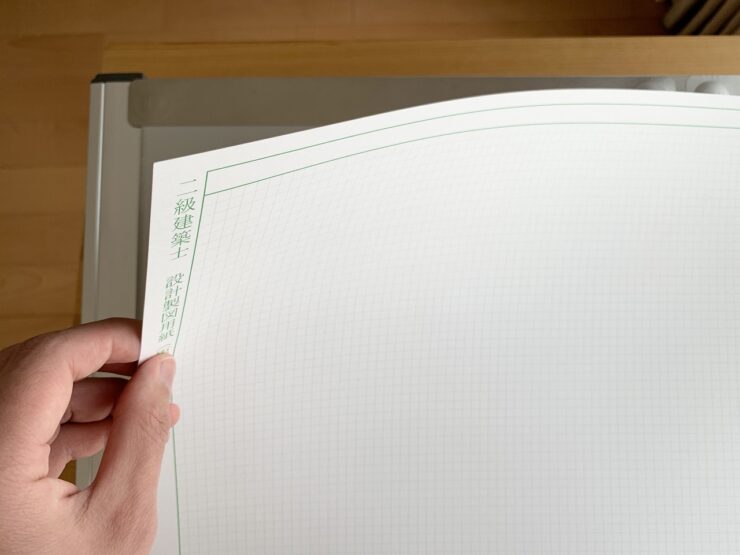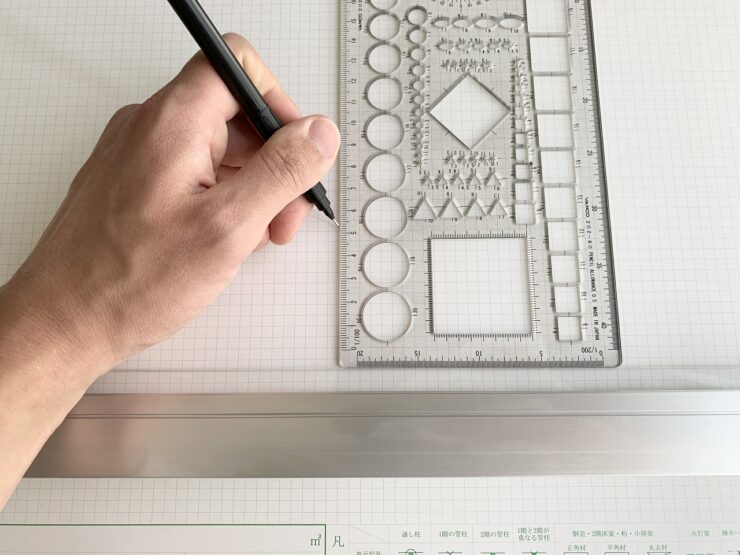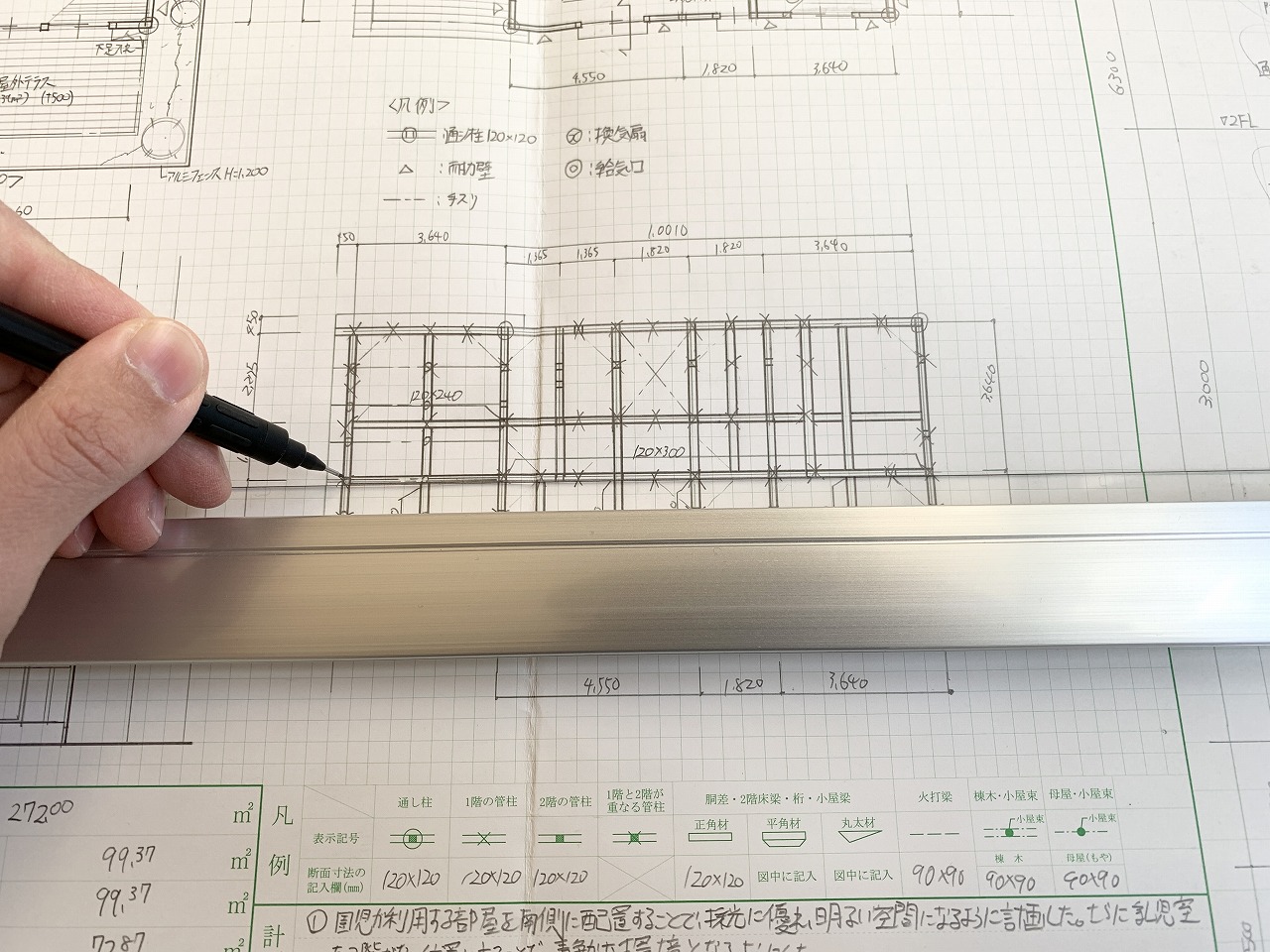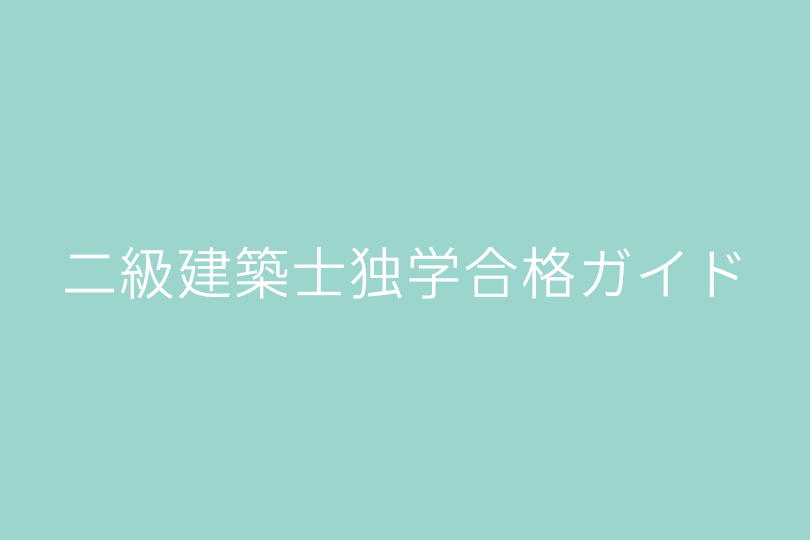こんにちは!二級建築士合格者のくりです。
ぼくも平行定規を使い何十枚と図面を書いて、無事合格しました。
※製図板はただの板で、それに動く定規がついたものを平行定規と言います。
しかし、平行定規にも色々な種類があり、選ぶのに迷ってしまいます。
そこでここでは、特徴別にまとめました。↓
- 定番・ベーシック
- オシャレ
- 軽量
- 全部入り
- 安い
あと、合格できたぼくが使っていたものも紹介します。
二級建築士の製図試験で使う、A2平行定規選びの参考になれば幸いです。
この記事は、「【合格者が選ぶ】二級建築士試験で使えるA2平行定規おすすめ7選(製図板)」を書いていきます。
※先に言うと、コクヨの平行定規を使って合格しました。基本的に、これを選べば間違いなしです。↓
目次
平行定規の使い方
まずは平行定規の基本的な使い方を説明します。
二級建築士製図試験の当日も、この流れでセットします。
- STEP
机に平行定規をセットします。

- STEP
製図用紙をセットします。

- STEP
付属マグネットか、ドラフティングテープで固定します。

- STEP
サイドのロックを緩め、定規部分を動くようにします。

- STEP
製図用紙の線と定規部分を合わせ、ロックします。

- STEP
横に線を引けるようになります。

- STEP
縦の線は、テンプレートなどを利用します。

以上、平行定規の使い方でした。
初めは難しいですが、慣れてくればササッとセットできるようになります。
二級建築士試験で使える平行定規の選び方

次は平行定規の選び方を解説します。
ただ正直、選び方は、
特になし
です。
強いて言うなら、「有名メーカーのものを選ぶ」くらいです。
製図試験を独学で合格した経験から思うに、
製図の練習量を重要度100とすると、平行定規選びの重要度は0.5です。
- 製図の練習量:重要度100
- 平行定規選び:重要度0.5
なので平行定規を早く手に入れて、すぐに製図の練習をすることが合格への近道です。
少なくとも、「この平行定規を選んだから失敗した」という意見は聞いたことがありません。
有名メーカーの物を選べば間違いないです。
サクッと手に入れて、早く製図の練習に移りましょう。
選ぶ際の注意点3つ
ただし、3つの注意点があります。↓
- 特殊な平行定規は選ばない
- 中古品は避ける
- 学科試験中に購入する
1.特殊な平行定規は選ばない
斜めの線が書けたり、自由の伸び縮みするなど、特殊な平行定規はNGなので選ばないようにしましょう。
※出典:「設計製図の試験」において使用が認められる平行定規と型板について.pdf|公益財団法人 建築技術教育普及センター
なおここで紹介しているものは全て、試験に対応しているシンプルな平行定規です。
2.中古品は避ける
中古品は、
- 変な癖がついていたり、
- 試験当日運悪く壊れる可能性がある
などギャンブル過ぎるので、避けるのが賢明かなと。
ぼくも人の平行定規を使ったことがあるのですが、変な癖がついていたり、欠けた部分にシャーペンが引っかかるなど、小さなストレスが度々ありました。
それならば「新品を買って受かったら売る」方が良いと思います。
3.学科試験中に購入する
あと学科が終わるとみんな一斉に買います。
なので、売り切れが続出します。
平行定規ではないのですが、ぼくもテキストを学科後に買おうとしていました。
そして終了後買おうとすると、すでに売り切れ、再入荷までの1週間も手がつけられない状態になりました。
「ただでさえ製図までの期間が短いのに、、、」とかなり歯痒い思いをしました。
ということで、試験を申し込んだ時点で買うことをおすすめします。
平行定規があれば、「絶対に学科受かって、製図やるぞ…!」とモチベーションも上がります。
二級建築士試験で使えるA2平行定規おすすめ7選(製図板)
ここから、二級建築士試験で使える平行定規おすすめ7選をご紹介します。
ここで紹介するものには全て、持ち運ぶためのキャリングケースが付いています。
比較表はこちら。↓(名称をタップすると、Amazonの詳細ページを見られます)
| No. | 名称 | 重さ | カラー | 値段 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コクヨ トレイザー | 約3.4kg | シルバー | 約3.2万円 | 定番・ベーシック |
| 2 | ステッドラー 平行定規 | 約3.2kg | シルバー | 約3万円 | 定番・ベーシック |
| 3 | 武藤工業 平行定規 | 約3.1kg | 黒 | 約3.6万円 | オシャレ |
| 4 | マックス 平行定規 | 約2.8kg | シルバー | 約3.3万円 | 軽量 |
| 5 | 武藤工業 平行定規 UT-06 | 約2.9kg | 黒 | 約4.4万円 | 軽量 |
| 6 | ドラパス 平行定規セット | 約3.0kg | シルバー | 約4.2万円(セット価格) | 全部入り |
| 7 | ドラパス 平行定規 | 約3.0kg | シルバー | 約2.9万円 | 安い |
※値段は記事作成時点のAmazon価格。
定番・ベーシック
コクヨ|トレイザー 平行定規 マグネット製図板 A2
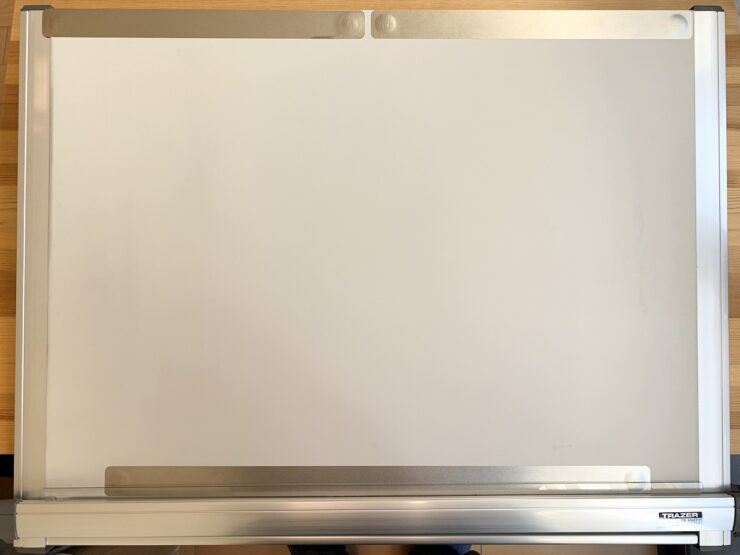
コクヨのA2平行定規。
ぼくが使っていた平行定規です。

平行定規を選ぶ時、
「まあ日本メーカーのコクヨなら間違いないだろう」
と思って買いました。
重量は3.4kgと、少し重めです。
ただルンバで何度か倒してしまい、そのたびに「ガシャーン」となっていたのですが、不具合なく使っていました。
少し重い分、頑丈なのかもしれません。
そしてこの平行定規で何十枚と図面を書き、無事合格しました。
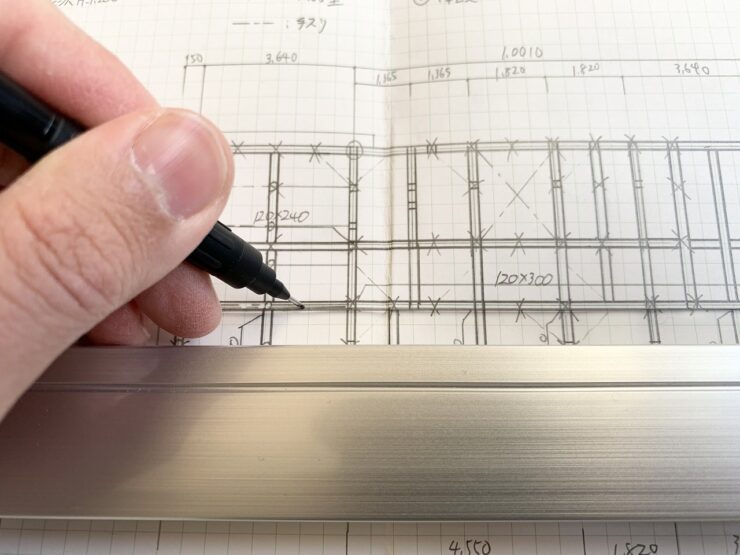
ぼくの相棒です。感謝感謝。
基本的に、これを買っておけば間違いなしです。↓
ステッドラー|平行定規 A2 マルスライナー 960
ドイツブランド「ステッドラー」が発売する、A2平行定規。
試験会場でよく見かけました。
こちらも大人気の製図板です。
本体3.2kgで、コクヨのものより0.2kg軽いです。
オシャレ
武藤工業|平行定規 ライナーボード
武藤工業が販売する、A2平行定規 ライナーボード。
シングルベルトで動かすので、精度の高い図面を書くことができます。
この黒いスタイリッシュな平行定規も、試験会場でよく見かけました。
1年間のメーカー保証もあるのが嬉しいポイント。
軽量
マックス|定規 平行定規 軽量タイプ A2サイズ
マックスの軽量A2サイズ平行定規です。
本体は2.8kg。なんと3kgを切っています。
製図板は、製図学校・模試・本番などでよく持ち運ぶことになります。
そこで結構肩に負担がかかるんですよね…。
しかしこの軽量タイプなら、ライバルより体力を消耗せずに済みます笑。
家でも机にセットするときに必ず動かすので、軽いほうがいいですね。
武藤工業|平行定規 ライナーボード UT-06 A2サイズ
武藤工業の平行定規 ライナーボード A2サイズ。
ワイヤー・プリーを使い、0.2kgの軽量化に成功しています。
少しお高めですが、本体2.9kgと3kgを切っています。
全部入り
ドラパス|A2平行定規+製図用具セット
ドラパスのA2平行定規と製図用具セット。
平行定規のほかに、試験で使える製図道具がセットになっています。
「色々選ぶのがめんどくさい、早く図面書きたいな!」
と思っている方におすすめです。
安い
ドラパス|A2平行定規
ドラパスのA2平行定規。
ほかの平行定規と比べる、格安で手に入ります。
もちろん建築士試験に対応しています。
二級建築士試験で使える平行定規おすすめ7選 まとめ
この記事は、「【合格者が選ぶ】二級建築士試験で使えるA2平行定規おすすめ7選(製図板)」を書きました。
平行定規にも、色々な種類があります。
正直価格は高いですが、
- 二級建築士を取ることができ、
- さらに一級建築士にも使える、
と考えたら、損する買い物ではないなと。
もし迷ったら、コクヨの平行定規を選べばオッケーです。
ぼくが使って合格できた平行定規なので。
以上です。応援しています!
比較表はこちら。↓
| No. | 名称 | 重さ | カラー | 値段 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コクヨ トレイザー | 約3.4kg | シルバー | 約3.2万円 | 定番・ベーシック |
| 2 | ステッドラー 平行定規 | 約3.2kg | シルバー | 約3万円 | 定番・ベーシック |
| 3 | 武藤工業 平行定規 | 約3.1kg | 黒 | 約3.6万円 | オシャレ |
| 4 | マックス 平行定規 | 約2.8kg | シルバー | 約3.3万円 | 軽量 |
| 5 | 武藤工業 平行定規 UT-06 | 約2.9kg | 黒 | 約4.4万円 | 軽量 |
| 6 | ドラパス 平行定規セット | 約3.0kg | シルバー | 約4.2万円(セット価格) | 全部入り |
| 7 | ドラパス 平行定規 | 約3.0kg | シルバー | 約2.9万円 | 安い |